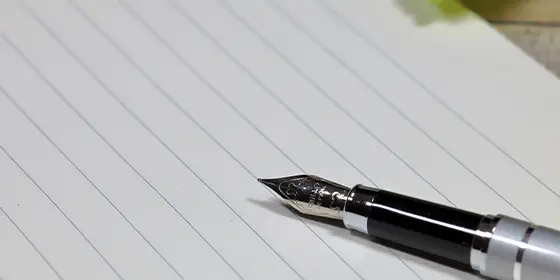特別受益財産の範囲
遺贈された財産
目的を問わずして、すべて特別受益財産として持ち戻しの対象になります。遺贈された財産は、相続開始の時点では相続財産に含まれているもので、贈与された財産のように加算する必要はありません。
婚姻、養子縁組のための贈与
特別受益財産の範囲に含まれます。持参金、支度金など、婚姻・養子縁組のための支度の費用が典型的なものです。結納金、挙式費用が、婚姻、養子縁組のための贈与に含まれるかについては争いがあります。
挙式費用については、通常の挙式費用は含まれないとする考えが有力です。この考えには、挙式は婚姻、また養子縁組をする当事者のためというよりも、親の社交上の出費たる性質が強いことを理由とする見解があります。
生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与とは、子どもが独立する際に居住用の宅地を贈与したり、農家なら農地を贈与したりというのが典型的なものですが、これらに限らず、広く生計の基礎として役立つような財産上の給付が該当するとされています。
また、日本の教育水準をみても高校や大学の教育を、義務教育の場合に準じて考えることができると言えます。このような高等教育の費用は、被相続人の生前の資産収入や社会的地位から、その程度の教育をするのが普通であるという場合には、学費の支出は親の当然なすべき扶養の範囲として特別受益に該当はせず、それを超えた身分不相応な学費のみが特別受益となると考えられます。
生命保険金請求権
被相続人からの生前贈与あるいは遺贈には、条文の分離上該当しません。しかし、被相続人が保険料を支払った場合、保険金請求権は保険料の対価である実質があり、遺贈や死因贈与のように財産の移転(無償処分)とみられて、その形式にとらわれずに、遺産分割に際して、共同相続人の衡平をはかるため、持ち戻しの対象にすべきという考えもあります。
なお、最高裁判所決定平成16年の判例では、養老保険契約にもとづく死亡保険請求権は、被保険者が死亡したときにはじめて発生するものであり、保険契約書の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないため、実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたとせず、相続財産であることを否定し、死亡保険金請求権の特別受益性を原則として否定しました。
死亡退職金
死亡退職金などの遺族給付は、給料の後払いのような性質があることと、持ち戻しを否定すると共同相続人間の実質的衡平が難しくなることなどを理由に、生命保険金請求権と同様に、その特別受益性を肯定しています。
特別弔意金につき、遺族の生活保証的性格を有することを理由に、特別受益性を肯定したのがあります。また、退職金、役員功労金につき、いずれも被相続人の生前の労働、貢献に対する対価であり、特に退職金は賃金の後払いのような性質があり、その実質は遺産に類似するといえ、共同相続人間の公平をはかるために、特別受益財産とみるのが相当であるとした判例があります。
特別受益持戻免除の意思表示
特別受益財産が持ち戻されるのは、共同相続人間の衡平をはかる目的と、それが被相続人の通常の意思に合致していると推測されることからです。被相続人がこれと異なる意思、つまり持戻し免除の意思を表示したときは、遺留分を侵害しない限りこれに従うことになります。この持戻し免除の意思表示は、被相続人に対し、特定の相続人に相続分の他に特に利益を与える権限を認めたものであって、共同相続人間の衡平より被相続人の意思を優先させた、ということになります。
持戻し免除の意思表示の方法は、特に定められていません。生前行為か遺言で記すかなど、定められていません。被相続人が特定の相続人に、相続分のほかに、財産を相続させる意思があったことを推測させる事情がある場合に、黙示の持戻し免除の意思表示が認められます。
また、被相続人が特定の相続人に生前に贈与をしたにもかかわらず、この贈与に言及することなく、遺言で相続分を指定した場合には、被相続人は持戻し免除の意思を表していると考えてよいでしょう。
遺言で持戻し免除の意思表示がされている場合に、撤回が許されていることは明らかです。しかし、生前行為によって持戻し免除の意思表示を撤回できるかについては少々疑問がありますが、被相続人に遺産の自由処分権が認められていることからすれば、自由にできると考えられています。