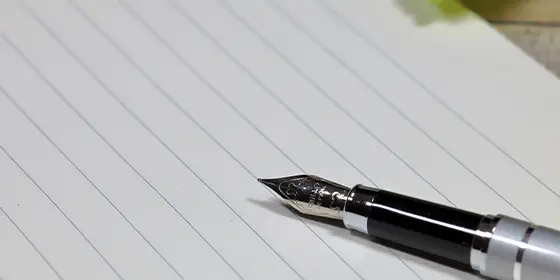代襲相続人の相続分
第901条
1.第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2.前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
相続人となるはずだった親が死亡し、相続欠格や廃除により相続権がなくなり、子が代わって相続権を持つ場合、子の法定相続分は親が持つはずだった法定相続分を承継します。ただし、子が複数いる場合は、親が引き継いだ法定相続分を均分します。また、本来相続人となるはずだった兄弟姉妹が死亡し、相続欠格や廃除により相続権がなくなり、その子(被相続人からすると甥姪)の法定相続分は、親(被相続人からすると子)が持つはずだった法定相続分を承継します。ただし、子が複数いる場合は、親が引き継いだ法定相続分を均分します。
遺言による相続分の指定
第902条
1.被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。条の規定に従ってその相続分を定める。
2.被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
被相続人は、法廷相続人にかかわらず、遺言書に各相続人の相続分を指定したり、その指定を第三者に委託することができます。ただし、相続分の指定をしたり、第三者に指定を委託したりしても、遺留分については侵害することができません。また、被相続人が共同相続人の一部の人の相続分のみを指定したり、第三者に指定させたりした場合は、残りの相続人の相続分は法定相続分の規定によって定めます。
本条は、遺言による相続分の指定について規定しています。被相続人が相続分を指定する他にも第三者への委託をすることも可能です。『遺言で第三者への委託ができる』というより、第三者が相続分を指定する方法の定めがない殿です。委託された第三者が、指定を引き受けるかどうか不明にしたままの場合、相続人は相当の期間を定めて催告することができます。その期間内に指定がなければ委託は失効し、委託を引き受けた第三者が相続を指定しない場合も失効します。
指定をした際の効力は、被相続人による指定の場合、死亡のときを効力の開始とし、第三者による指定の場合、相続開始時にさかのぼって効力が生じます。
相続分指定があっても、それによって具体的相続分が確定するのではなく、第903条の特別受益の持ち戻し、第904条の2の寄与分が影響するためです。特別受益に関しては、持ち戻し免除の意思表示が認められていますので、相続分指定の意思表示があった場合には、原則として持ち戻し免除の意思表示も合ったと解釈されるでしょう。一方、寄与分には持ち戻しの免除の意思表示がないため、寄与分が認められる場合には、条文の具体的相続分は指定された割合とは異なることになります。
なお、相続財産のなかの特定財産を特定の相続人に与えるという旨の遺言がされた場合のことであり、その相続財産の価値が法定相続分によって算定される額を超えるときには、相続分の指定を含む遺産分割方法の指定であることを前提にした判例があります。
相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
第902条の2
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
本条は、平成30年の民法改正において新設されました。基本的にはこれまでの判例の準則を明文化したものです。本条は、相続分の指定があった場合でも、相続債権者は各共同相続人に対し法定相続分の割合に応じて分割された債権を行使できることを定めています。
被相続人による最後の意思による処分の効力は、相続債権者には当然およばないことを前提にしています。法定相続分よりも小さい相続分を指定された共同相続人が法定相続分に応じた相続債務を弁済した場合は、共同相続人の間で求償の問題として処理がされます。
本条の但書は、相続債権者が相続人の一人に対して、その指定された相続分に応じた債務の承継を認めた場合には、それ以降のさ権利行使は指定相続分に応じたものになる旨を定めています。債務の承認は共同相続人のうちの一人にすれば共同相続人全員に対して効力を生じるという趣旨です。認められた共同相続人が他の共同相続人に対してその事実を知らせなかったことによって、他の共同相続人がその者の指定相続分を超えた額の弁済をした場合には、相続債権者に対する不当利得返還請求権が成立します。