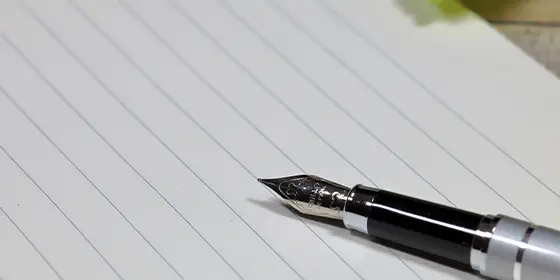相続分とは
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
本条は、相続人が複数人いる場合において、各相続人が持つ権利義務の割合を定めたものです。つまり相続分は法定相続分という理解です。相続人が複数人いるとき、相続人を共同相続人といいます。
共同相続人の権利義務
不可分債権・不可分債務
たとえば1枚の絵は性質上、分けることができません。このように性質上不可分である債権義務については、共同相続人に分割帰属をしないと理解されています。
可分債権・可分債務
金銭債権・債務のような分けることができる可分債権は、相続開始とともに共同相続人間で法定相続分の割合で分割され、遺産分割の対象とはしないという考えが多いです。これに対し、可分債権・可分債務が分割されると相続債務者・相続債権者の不利益になる恐れがあるため共同相続人間で不可分債権・不可分債務になるという考えもみられます。
ですが、近年は最高裁が、預貯金債権の他に定期預金債権や定額郵便預金再建、株式・委託者指図型投資信託の契約にもとづく受益権・外国投資信託にかかる契約にもとづく受益権・個人向国債などを例外として認めています。
なお、預貯金債権が分割の対象と理解された時期から、分割をする前の払い戻しについて、これまで銀行実務は無権利者への支払いがないようにするために、共同相続人全員からの請求が必要としてきました。しかし、2018年の改正により預貯金債権の一部に限り、相続人が単独でも権利を行使する余地が認められました。
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
連帯債務
第三者の金銭債務について、連帯債務者となった者が死亡し、その連帯債務が共同相続された場合も、相続人たちは分割された債務を承継して、各自承継した範囲で本来の債務者と共に連帯債務者になると解釈されていますが、本来の債務者と各相続人との間に債務額が異なる連帯債務が生じたり、共同相続人の間に連隊関係を認めないかという法律上の問題が生じたりするため批判的な考えも存在しています。被相続人が負担していたのと同様に連帯債務を共同相続人が不可分的に負担すると解釈するケースが多いのが現状です。
金銭
金銭と金星債権は区別しています。金銭は非相続人の死亡によって共同相続人の共有財産となります。相続人は非相続人の残した遺産に法定相続分に応じた持分権を取得するのみで、金銭債権のように相続分に応じて分割された額を承継するものではありません。それがもし相続開始後に現金が金融機関に預けられて債権化されても、相続開始時にさかのぼり金銭債権となるものではないため、遺産分割をするまでの間には自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできません。