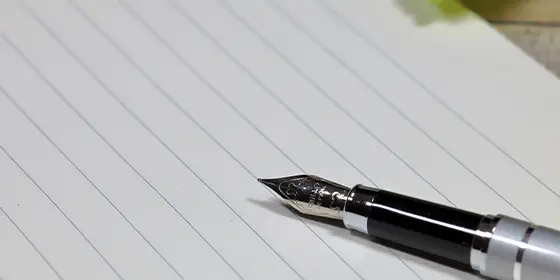祭祀財産の承継
第897条
1.系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
1947年に家督相続制が廃止され、祭司に関しては平等相続の督促が定められました。系譜、祭具、墳墓、を相続財産からはずし、一般の相続とは区別して承継者を定める規定です。

| 系譜 | 先祖から子孫に至る一族代々の図表である家系図 |
|---|---|
| 祭具 | 位牌、仏壇、仏像、神棚、神体、神具、仏具、庭内神祠などの祭祀や礼拝に用いる器具や道具 |
| 墳墓 | 墓地、墓石、墓碑など |
本条は、系譜や祭具、墳墓などの祭祀財産は、被相続人が暮らしていた環境の慣習によって、承継する人を決定することを規定しています。ただし、被相続人が遺書を残すなどして祭祀財産を承継する人を指定していた場合は、指定された人が承継します。指定された人は、原則断ることができませんが、他の人に権利を譲ることはできます。遺言がなくても、口頭や書面などの生前行為でも差し支えないとされています。
慣習による決定は実は少ないケースです。その地域の慣習や属した職業などの慣習を明らかにすることが難しいためです。
さらに二項では、遺言書による指定がない場合、暮らしていた環境の慣習が明らかでない場合、祭祀財産を引き継ぐ人は家庭裁判所が決定することになります。家庭裁判所で「祭祀継承者指定の申立て」という手続きで祭祀財産を引き継ぐ人が決定します。
家庭裁判所は、被相続人との関係や祭祀財産を引き継ぐ意思や能力があるかなどを基準に調停がなされるようです。たとえば、長男であるとか、氏(苗字)が同じであるとか、親族かなどを問うのではなく、生活上の関係や、これまで墓地を管理していたかなどが重視されています。
なお、祭祀財産を承継するのは一人とは限りません。複数人で分けた判例も存在しました(東京高判昭和62年10月8日)。系譜と墳墓を別々に承継するというような分け方です。
祭祀財産を承継した者の地位
祭祀財産を承継した人に祭祀を行う義務が生じるわけではありません。通説では、祭祀財産の承継に承認や放棄の概念がありませんので、前述した通り、断ることができず辞退するなどができません。ですが、承継した後に、祭祀財産の処分は承継した人の自由です。
遺体・遺骨の承継
祭祀財産である墳墓に埋葬された遺体や遺骨は、祭祀を主宰するべき者に帰属する、と祭祀財産に含まれる判例があります(最三小判平成元年7月18日)。これに対し、通説は被相続人の遺体・遺骨の帰属について、慣習に基づいて喪主に帰属するという原始的な考え方もあるのは確かです。