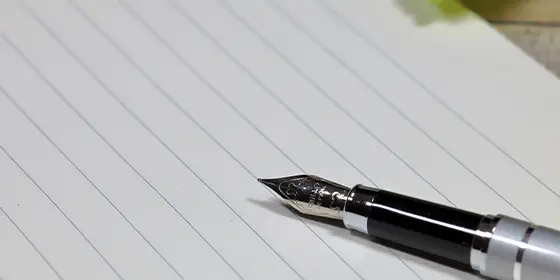相続人の資格の重複
相続人としての資格が重複する場合があります。つまり、一人に2つの相続人としての身分が重なる場合があるということです。民法上、法定相続人になりえるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。一人の相続人が、重複してこれらの身分を持ち合わせるケースが存在します。
相続人としての資格が重複した場合、相続分の決定は民法に明確に定められているわけではありません。遺産の割合は相続人がどれだけの法定相続分を有するかが重要です。
第887条
1. 被相続人の子は、相続人となる。
2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第889条
1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹
重複した資格の例
ケース1
祖父母が孫を養子としたケースでは、子と孫としての身分の重複から相続資格が重複します。
ケース2
父母が子の配偶者を養子としたケースでは、配偶者と兄弟姉妹としての身分の重複から相続資格が重複します。
ケース3
被相続人の実子長男・次男・長女といた場合に、長男が長女を養子とし、のちに長男が死亡、その後被相続人が死亡した場合、被相続人の長女は被相続人の子としての相続資格と、長男(兄)の子(養子)としての代襲相続人となる相続資格が重複します。
登記実務
養母の養子となっている夫婦(夫A・妻B)において、妻Bは夫の妹でもあります。戸籍・除籍謄本および相続放棄申述受理証明書のほか、妻Bの配偶者として相続放棄をしたことを確認できる相続放棄申述書の謄本、さらに夫(兄)の妹としては相続放棄をしていない、とした相続登記の申請について、これを受理して問題ないとしています。
ほかの例では、被相続人の養子が相続放棄をして、のちに死後認知の裁判が確定しても、その養子は非嫡出子としての相続権を持っていないとしたものがあります。認知には遡及効(さかのぼって効力が生じる)があるため、相続開始のときには非嫡出子であったことになります。しかし養子と非嫡出子という資格は、相続関係では両立しないとしたものです。