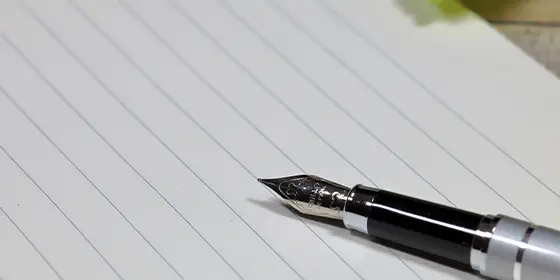相続の手続きをするには、どのような相続人がいるかを調査して相続人を確定しなければなりません。誰が相続人であるかは戸籍によって決まっていますので、戸籍を調べれば把握できます。しかし必ずしも明らかでない場合もあります。胎児の存在や、相続人の行方がわからない場合、婚姻外に子がいる場合などです。
胎児がいる場合
母体に胎児がいる場合、胎児は必ず出生するとは限りらなく、死産の場合もありえます。
胎児がいる場合も、胎児を除外して遺産分割をするのも有効という説もあります。胎児が出生したのちに民法第910条を類推適用するというものですが、この考え方は胎児の保護に薄いともいえます。
民法第910条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
特別代理人を選任して、胎児に代わり遺産分割協議ができるという説もあります。しかしこの場合は、もしも死産であった場合に困ります。また、胎児が双生児であると判明する前に遺産分割協議をし、双生児出生の場合も困ります。
胎児が現に出生するまで相続人の数が不明として、遺産分割協議を待つのがよさそうです。
相続人が相続承認後に行方不明の場合
相続人が相続を承認後に行方不明となった場合は、遺産分割協議ができないことになります。民法第907条第2項の適用となります。
第907条2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
つまり家庭裁判所で遺産分割の審判ができます。
相続人が相続開始当時から行方不明の場合
存在している相続人が、相続開始当時から行方不明の場合は、不在者財産管理人を選任し遺産分割協議ができます。
相続開始後で遺産分割協議前の死亡
行方不明の相続人が相続開始後で遺産分割協議前に死亡していたことが判明した場合は、相続人は存在した相続人の確定に重大な過誤はありません。行方不明で死亡した相続人の相続人となる者が、遺産分割協議に参加します。
同時死亡の推定がある場合
同時死亡の推定とは、たとえば父と子が同じ事故で死亡したような場合です。この場合、死亡者相互間には相続はおこりません。被相続人の先死が確認できる場合以外は、遺産分割協議を控えるべきです。
相続人身分の消滅が争われている場合
相続欠格・相続人の廃除・嫡出否認・親子関係不存在・婚姻または縁組の無効などが争われている場合がありますが、これらに該当する場合は、当該事件が解決し明確な判定が出るまで、遺産分割協議をすべきではありません。
被相続人の死後に認知の訴が提起された場合
被相続人が亡くなったあとに認知の訴がなされる場合があります。しかし戸籍上の相続人だけで、すでに遺産分割協議がされていた場合は有効です。民法第910条は有効を前提としています。
民法第910条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
遺産分割協議を有効として、後に認知によって相続人に確定した者に、価額支払請求を許せばよいとしたのです。