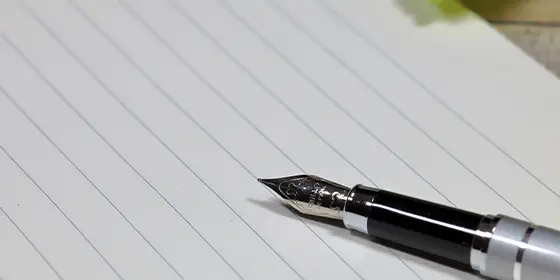遺産分割協議書の効力
遺産分割協議をしたのちに遺産分割協議書を作成します。遺産分割の効力は、相続開始の時点にさかのぼります。遺産分割協議書は作成日から効力が発生するのではなく、被相続人がなくなった時までさかのぼり効力が発生するということです。相続開始後に遺産分割がされ遺産分割協議書が作成されたら、被相続人から相続した相続人個々人の財産になります。
遺産から生じた果実
被相続人から相続して相続財産の範囲が決定されるのは相続開始のときです。しかし、相続の開始時には果実は生じていません。遺産分割までに年月が経っていて、しかもその果実が財産的な価値がある場合に問題になります。
相続の効力は被相続人が亡くなったときに発生しますので、遺産分割後に生じた賃料債権などの果実は、遺産分割協議書でその財産(たとえば賃貸した家屋)を取得した相続人に、帰属することになります。
最高裁判所の判例は、相続開始後、遺産分割が決定するまでの間に生じた果実の帰属に関して、「相続の場合に、遺産分割が決定するまでの間に、遺産の賃貸不動産から発生した賃料債権は、遺産とは別の財産と考え、分割単独債権とすることが相当である」と判断しました。
つまり、相続開始後に発生した賃料債権は、遺産分割としては対象外ですが、分割して相続人に相続がされるとしています。さらに、最高裁判所は各共同相続人が確定的に取得した財産の帰属は、後の遺産分割に影響を与えないとしました。
この結果は、賃料債権の分割、清算は訴訟手続きによらなければなりません。なお、相続人全員が合意をすることで、遺産分割の対象とすることができます。
遺産分割協議書と登記
遺産分割協議書を作成した場合に、第三者に対して自分が所有者であると主張するためには、登記が必要かという問題です。
最高裁判所の判例は、遺産分割の際に、実質上は持分の移転があるということから、持分を超えて取得した場合に対抗要件を求めています。遺産分割が、実質的に有している移転的な性質を考慮して、分割により新たな物権変動が生じたものと考えて、対抗関係にあると判断しました。
相続開始後の持分処分
たまにあるケースですが、遺産分割協議書が作成されていないのに、相続人の一人が単独で登記をして第三者に譲渡し、移転登記をするという例です。判例では、他の相続人は自己の持分に関して登記していない状態で対抗するとしています。登記に公信力はありませんので、登記を信じても保護はされません。他相続人の持分は他人の財産であり、第三者は取得することができません。
処分された財産は、他の相続人と第三者との共有になり、保護される特定財産の持分を譲渡された第三者は、譲渡人以外の相続人に対して自己の権利を主張するためには登記が必要です。
相続と登記
相続は包括承継です。したがって、被相続人から譲り受けたものと、相続人から譲り受けたものの関係は、被相続人と相続人は同一人と考えられますので対抗関係になります。これに対し、被相続人から譲り受けたものと相続人の関係は対抗にはなりません。
遺産分割協議書の決定で、登記をする場合には次の二通りの方法があります。
- 被相続人名義から直接移転登記をする方法
- 一旦共同相続人によって共同登記をして移転登記をする方法
直接被相続人名義でする登記は一般的な登記ですが、この場合には遺産分割協議の結果、その財産を取得した相続人の単独申請で登記します。
この相続による共有登記は、保存登記であり共同相続人が単独で登記することもできます。共有登記から遺産分割後にする持分移転登記は共同相続で行います。
遺産分割協議書と第三者
遺産分割協議をし遺産分割協議書を作成した場合、相続開始の時点にさかのぼって効力が発生しますが、第三者の権利を侵害することはできません。
第三者とは、個々の遺産の共有持分を譲り受けた者や担保権を取得した者のことです。この場合、その持分の範囲でのみ有効なもので、それ以上の効力はありません。
そのほか、差押え債権者も第三者として保護されています。これは共同相続人の一人の債権者が、その者の共有持分を差し押さえる場合に該当します。
第三者の保護、すなわち遺産分割協議書で遺産を取得した相続人に対し、第三者が保護されるためには、不動産の場合では登記が必要にです。同じく動産であれば、動産の対抗要件である引渡しが必要です。