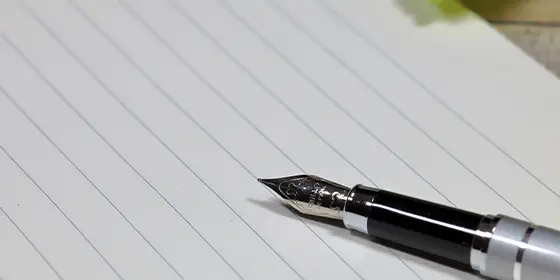遺産分割協議とは、相続人たちが被相続人の財産を誰がどのような割合で相続するかを協議するものです。まれに質問されることもありますが、遺産分割は5人なら5人でピッタリ5分の1ずつ分割しなければならないということではありません。遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、現物分割・換価分割など、どのような分割方法でも可能とされています。
たとえば、共同相続人のうちの一部の者の取得分を0(ゼロ)にすることも可能です。ただし、負債は負担しなければなりません。
被相続人が遺言で分割の割合を指定している場合は、共同相続人の協議で遺言の指定と異なる協議をすることも可能とされています。たとえば、一人の相続人にすべての財産を取得させることもできるということです。ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言に記載されている相続分の指定に従わなければなりません。
「遺産分割をする相続人」で説明のとおり、いつでも遺産分割をすることができます。被相続人が亡くなってすぐに遺産分割しなければならないということもなく、いつまでに遺産分割しなければならないという期限もありません。ただし、被相続人が遺した遺言で禁じた場合は、遺言に従わなければなりません。
遺産分割協議書
遺産分割協議書には、どの相続人が何を相続したかを記載します。あわせて相続人の氏名や住所、実印の押印と印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議で決定されたことを記した遺産分割協議書は、のちのトラブル防止のためにも作成するのがよいでしょう。遺産分割協議書は、遺産分割協議をしたら必ず作成しなければならないということではありません。遺産分割協議書を作成する義務はなく、作成しないことで遺産分割協議の内容が無効になることもありません。しかし、法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きに遺産分割協議書が必要になりますので、一般的に遺産分割協議がされた後には遺産分割協議書を作成しています。
遺産分割の禁止
遺産分割を禁止する方法は次のとおりです。
遺言による遺産分割の禁止
被相続人が遺言で遺産分割を禁止した場合、共同相続人全員の合意があっても、禁止された期間内には遺産分割をすることができません。遺言による分割禁止期間は相続開始から5年以内に限られます。5年を超える分割禁止期間は、遺言書に記載があっても無効になります。
共同相続人の合意による遺産分割禁止
共同相続人で協議をして合意のうえ、遺産分割を禁止することができます。禁止期間は5年以内に限られます。遺産分割が完了していない期間の相続財産は相続人全員の共有財産になります。禁止期間中に共同相続人が合意して遺産分割をした場合は、遺産分割禁止が解かれ、遺産分割協議が有効となります。
家庭裁判所審判による遺産分割の禁止
共同相続人は遺産分割協議の合意がなされないと遺産分割を家庭裁判所に請求することができます。その際に、特別な事由によって家庭裁判所が遺産分割禁止を審判される場合があります。特別な事由とは、それぞれ個々によりますが相続人の能力や遺産の範囲などの争いが複雑だったり、共同相続人にとって遺産分割をしない方がよい場合だったりが考えられる場合です。
相続債務の遺産分割
被相続人の財産は相続人へ相続されます。その財産がプラスの財産であってもマイナスの財産(借金やその他の債務)であっても相続されます。被相続人が生前にもっていたマイナスの財産がそのまま相続人へ相続されます。
遺産分割は共同相続人が、相続財産をだれにどのような割合で分割するかを協議するものですが、マイナスの財産は遺産分割の対象になりません。遺産分割はプラスの財産についてのみ行います。相続人の一人が全債務を相続するという遺産分割協議が成立しても、債権者は協議内容を無視して、他の相続人に債務の履行を請求できます。つまり、可分債務の場合は、当然に各相続人の相続分に応じて、分割されて承継されます。相続された債務が不可分債務である場合には、各相続人が全部について履行の責を負うのです。