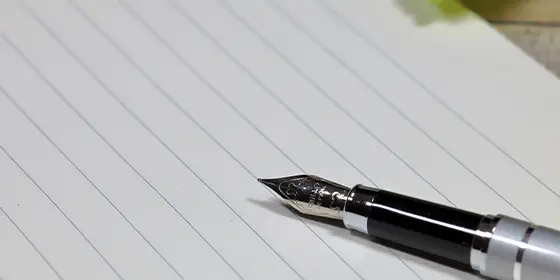同時死亡の推定
民法第32条では、同時死亡の推定について規定されています。
第3条
2.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
同時死亡の推定とは、たとえば、同一危難にあって親子が死亡して、どちらが先に亡くなったか、がわからないケースについては「同時に死亡したもの」と推定されます。
この場合、同一危難にあって親子が同時に死亡したとするわけですから、亡くなった子は親の相続人とはなりません。もしこの亡くなった子に、子(親にとっての孫)がいる場合は、代襲相続することになります。亡くなった親に配偶者があれば、配偶者と孫が相続をするということになります。
仮に同時死亡の推定が民法で規定されていなかった場合に起こりえることを考えてみます。
たとえば、祖母、父母、子の家族です。この家族の父と子が事故に遭い死亡しました。
- 子が父より先に死亡したと仮定すると、父の財産は母が三分の2、祖母が三分の1という割合で相続します。
- 父が子より先に死亡したと仮定すると、父の財産は子が二分の1、母が二分の1という割合で相続します。そして子の死亡による財産を母が相続するので、すべてを母が相続することになります。
このように死亡した者の順番によって相続が変わるのです。同時死亡の推定は、死亡の前後を区別しないということです。死亡者間での相続が認められませんから、孫の代襲相続が認められるということになります。
なお、同時死亡の推定は、必ずしも同じ危難である必要はありません。まったく別の場所で起きた危難であっても、さらに一方の死亡時刻が明らかで、もう一方の死亡時刻が明らかでないという場合でも同時に死亡したと推定されます。
さらに同時に死亡した者が二人だけではなく、三人以上であっても同様です。三人のうちの一人は死亡時刻がわかっていて、のこり二人の死亡時刻が判明しないとき、三人の同時死亡が推定されます。そして、その三人が別々の場所であっても同時死亡が推定されます。
同時死亡の推定の反証
同時死亡の【推定】というのは、年齢や体力、死体の発見場所、医学的推定などを判断材料とした反対の立証で覆すことができるということになります。
同時死亡の推定がされたのちに、さまざまな証拠から推定が覆され死亡の前後が明かになったとします。すでに同時死亡として遺産分割がされていた場合、真の相続人は相続回復請求をすることができます。
また、同時死亡の推定にしがたって、保険金や損害賠償などが支払われている場合、真の権利者が受け取るべきものを不当に取得したものとして、不当利得返還請求を受けることになります。悪意や過失がなかった場合でも、本来受け取るべきではなかったものとして、新たに判明した事実にもとづいて扱われることになります。
同時死亡の推定と遺言
上記の解説は、あくまでも法定相続分に則った考え方です。被相続人が遺言をのこしている場合は遺言の内容も考慮されることになります。
法定相続分は法律による基本的なもので、遺産分割協議によって異なる割合で遺産分割をすることも可能です。遺言をのこしていた場合は、(公正証書・自筆証書問わず)遺言が優先されることになります。