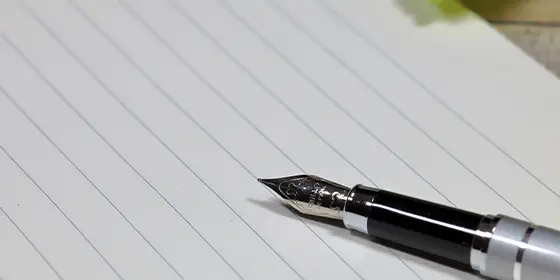相続とは
相続とは、亡くなった方の財産を配偶者や子などが相続人となって引き継ぐことです。相続は被相続人が亡くなったことにより当然に発生し、自動的に相続人に受け継がれることを意味しますが、相続人が複数人いたり、相続財産がプラスの財産だけでなく負債などのマイナスの財産も対象となります。相続の手続きは相続人にとって大きな負担となる場合もあるため、早めに取り掛かることが重要です。
-
相続とは
相続とは相続とは 相続の開始と場所 第882条 相続は、死亡によって開始する。 相続とは、亡くなった方の財産を承継することです。相続の原因は死亡によるのみで、隠居(生前に財産を譲渡するための旧民法の制度)による相続はありません。 生死不明の者に対する失踪宣告は、失踪者を死亡したとみなすことで相続が開始されます。認定死亡(生死を確認できない場合に、行政が死亡したと認定する制度)を受…
-
相続の効力
相続とは相続人は原則として被相続人のすべての権利義務を承継すること、および共同相続の関係についてから、一定の割合に一定の相続財産の価額を乗じた一定の数値の算出手順、さらに遺産分割の方針と方法についての規定を解説いたします。 相続の一般的効力 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 …
-
共同相続の効力
相続とは共同相続の効力 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 本条は、相続の開始から遺産分割までの共同相続人間の関係についてを定めています。 相続人が一人の場合は、被相続人の相続財産は単独で承継します。しかし相続人が複数人いる場合には、相続財産を全員が共有することになります。 遺言を残さなかった場合や遺言に残されていない相続財産がある場合は、遺産分割…
-
祭祀に関する権利の承継
相続とは祭祀財産の承継 第897条1.系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 1947年に家督相続制が廃止され、祭司に関しては平等相続の督促…
-
相続分
相続とは相続分とは 第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 本条は、相続人が複数人いる場合において、各相続人が持つ権利義務の割合を定めたものです。つまり相続分は法定相続分という理解です。相続人が複数人いるとき、相続人を共同相続人といいます。 共同相続人の権利義務 不可分債権・不可分債務 たとえば1枚の絵は性質上、分けることができません。…
-
法定相続分1
相続とは法定相続分 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めることによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相…
-
法定相続分2
相続とは前回に続き、法定相続分についてです。 https://souzoku-mima.com/souzoku/1824/ 法定相続人法定相続分配偶者と子配偶者は2分の1子は2分の1配偶者と親配偶者は3分の2親は3分の1配偶者と兄弟姉妹配偶者は4分の3兄弟姉妹は4分の1配偶者のみすべて子のみすべて親のみすべて兄弟姉妹のみすべて 法定相続分の問題 さまざまなパターンの法定相続分…
-
相続分指定
相続とは代襲相続人の相続分 第901条1.第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。2.前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。 相続人となる…
-
配偶者への特別受益・寄与分
相続とは配偶者への特別受益 民法第903条4項では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人はその遺贈または贈与について、持ち戻し免除の意思表示がされたものと推定すると規定されています。 特別受益である贈与が一定額を超えると、相続分がマイナスになる相続人がでてしまうことがあります。こ…
-
共同相続における権利の承継の対抗要件
相続とは第899条の21.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。2.前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権…
-
特別受益の相続分
相続とは特別受益の相続分 第903条1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。2.遺贈又は贈…
-
特別受益財産の範囲と特別受益持戻免除の意思表示
相続とは特別受益財産の範囲 遺贈された財産 目的を問わずして、すべて特別受益財産として持ち戻しの対象になります。遺贈された財産は、相続開始の時点では相続財産に含まれているもので、贈与された財産のように加算する必要はありません。 婚姻、養子縁組のための贈与 特別受益財産の範囲に含まれます。持参金、支度金など、婚姻・養子縁組のための支度の費用が典型的なものです。結納金、挙式費用が、婚…
相続人
被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。相続人は配偶者や子などの法定相続人だけでなく、被相続人が生前にのこした遺言書で相続人が定められている場合もあります。法定相続人として定められているのは配偶者と血族です。配偶者は常に相続人となり、血族は子や直系尊属(被相続人の上の世代である父母・祖父母など直系の血縁がある者)、兄弟姉妹が相続人と認められます。
-
相続人
相続人相続人 胎児の相続権利 第886条1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 本条は、相続に関する胎児の権利能力についてを規定しています。胎児が相続を開始しても権利能力を持っていませんが、生きて生まれた場合には相続開始時にさかのぼって相続人とするという考え方と、胎児が生きて生まれ権利主体となるが、死産の場合に…
-
相続人の欠格自由・廃除
相続人相続人の欠格事由 第891条次に掲げる者は、相続人となることができない。一 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。…
-
推定相続人の廃除
相続人遺言による推定相続人の廃除 第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡のときにさかのぼってその効力を生ずる。 被相続人が遺言書に特定の相続人を廃除する旨を書き記した場合に、遺言執行者は被相続人が死…
-
法定相続人
相続人法定相続 民法は、相続に関して法定相続制を採用しています。第一順位を子、第二順位を直系尊属、第三順位を兄弟姉妹という順位で血族相続人を定めています。先順位の者が相続人となれば、後順位者は相続人になれません。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいるときはその者と同順位で相続人となります。 法定相続人の組み合わせは4パターンになります。 配偶者と血族相続人 配偶者のみ …
-
配偶者の相続権
相続人配偶者の相続権の規定 配偶者が死亡した場合の相続について、民法第890条が定められています。婚姻の死亡解消に際して相続という方法で、財産関係の清算をするというものです。 民法第890条被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 死亡した配偶者の他方配偶者が相続人となるためには、婚姻…
-
相続人の調査
相続人相続の手続きをするには、どのような相続人がいるかを調査して相続人を確定しなければなりません。誰が相続人であるかは戸籍によって決まっていますので、戸籍を調べれば把握できます。しかし必ずしも明らかでない場合もあります。胎児の存在や、相続人の行方がわからない場合、婚姻外に子がいる場合などです。 胎児がいる場合 母体に胎児がいる場合、胎児は必ず出生するとは限りらなく、死産の場合もありえます。…
-
婚姻外の子・胎児の相続
相続人非嫡出子の相続権 婚姻関係のある間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、法律上婚姻関係にない間で生まれた子どものことを非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。いわゆる婚外子や隠し子です。 婚姻外の子どもも父親が被相続人の場合、その父に認知されていれば相続人となります。相続分については、平成25年12月の民法改正により非嫡出子も嫡出子も同額となります。(旧民法では、非嫡出子の相…
-
特別縁故者
相続人特別縁故者とは 特別縁故者とは、被相続人と特別親しい関係にあり、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる者のことをいいます。被相続人に法定相続人がいなければ、誰も財産を受け取ることはできません。相続人不存在の場合、最終的には国庫に納められることになります。 しかし法定相続人でなくても被相続人と特別に親しい者に財産分与を認めています。遺言がない限り財産を受け取ることがで…
-
養子の相続権
相続人普通養子縁組と特別養子縁組 普通養子縁組は、養子と実親との親子関係は継続したまま、養親と親子関係となります。特別養子縁組は、実親との親子関係を断ち、養親が養子を実子と同じ身分という扱いにすることです。 普通養子の相続 養子縁組によって養子となった者が、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。養子は、養親の嫡出子の身分を取得するので、養親の相続は実子と同じ順位で相続人とな…
-
相続人の資格の重複
相続人相続人の資格の重複 相続人としての資格が重複する場合があります。つまり、一人に2つの相続人としての身分が重なる場合があるということです。民法上、法定相続人になりえるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。一人の相続人が、重複してこれらの身分を持ち合わせるケースが存在します。 相続人としての資格が重複した場合、相続分の決定は民法に明確に定められているわけではありません。遺産…
-
相続欠格
相続人相続欠格 民法第891条に定めるとおり、相続人が相続する権利を失ったり、剥奪されたりする制度です。本来であれば相続できる権利をもつが、特定の事由によって相続人になることができなくなります。 ただし、相続欠格は別の相続に影響しません。たとえば、父親の相続で欠格事由に該当して相続権を失っても、母親の相続では関係ないので母親からの相続権は有効です。 また、相続欠格は代襲相続(被相続人…
-
相続人廃除・廃除の手続き
相続人相続人廃除 民法第892条に定めるとおり、推定相続人(相続が開始した場合に相続人になることが推定される人)に著しい非行がある場合、相続権を剥奪する制度です。 相続欠格と異なる点は、法律にもとづいて相続権を失うというのではなく、被相続人の意思にもとづいて相続権を失うということです。 第892条遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、…
代襲相続
被相続人の死亡よりも前に、相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が亡くなっているなどの場合に、その人に代わって相続人となることを代襲相続といいます。代襲されるのは被相続人の子および被相続人の兄弟姉妹に限られ、配偶者と直系尊属には代襲しません。相続開始の前に死亡すること以外に、相続欠格や廃除も代襲原因になります。
-
代襲相続
代襲相続代襲相続とは 代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人が相続権を失ったとき、他の者が相続人となる制度です。被相続人の死亡前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除あるいは欠格事由で相続権を失ったとき、その者の直系卑属が同一順位で相続人となることです。相続権を失った者は、被相続人の子および被相続人の兄弟姉妹で被代襲者といいます。被相続人の直系尊属(両親、祖父母)および配偶者には、…
-
同時死亡の推定
代襲相続同時死亡の推定 民法第32条では、同時死亡の推定について規定されています。 第3条2.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 同時死亡の推定とは、たとえば、同一危難にあって親子が死亡して、どちらが先に亡くなったか、がわからないケースについては「同時に死亡したもの」と推定されます…
相続放棄
被相続人の財産を一切引き継がず、相続人の立場でなくなることを相続放棄といいます。被相続人から引き継ぐ財産は、プラスの財産だけでなく負債などのマイナスの財産も対象となります。マイナスの財産を引き継がないようにするために、相続人の立場を捨てる相続放棄の手続きが必要になります。相続開始を知ってから原則3か月以内に申述しなければなりませんので、できるだけ早く取り掛かることが重要です。
-
相続放棄とは
相続放棄相続財産は、必ずしも相続をしなければならないということはありません。被相続人の財産を相続する権利のすべてを放棄することができます。相続放棄は、はじめから相続人とならなかった、とみなされるようにする意思表示です。『私は相続しません』と誰かに伝えたり、宣言したりすることではなく、相続権利を放棄する法律上の行為です。 かつて明治民法では家督相続を義務づけられていましたが、1947年の家族法改正に…
-
相続放棄の効力と管理
相続放棄相続の放棄の効力 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 相続放棄をした人は、相続開始時点にさかのぼり、そもそも相続人ではなかったという扱いになります。共同相続人がいる場合は、相続放棄によって共同相続人が減るため他の共同相続人の法定相続分が増えることになります。 相続放棄をした人が唯一の相続人であった場合は、次順位の相続…
-
相続放棄の注意点
相続放棄相続放棄の期限に注意 相続放棄をする場合に、もっとも注意が必要なのが期限です。相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述し、受理されなくてはなりません。 申述書の提出は共同相続人の判断は無関係で、当然申述にどなたかの承諾なども必要なく、本人単独ですることができます。ですから、共同相続人の判断や意思を待つ必要もありません。 相続放棄をするための3ヶ月の期間を熟…
-
相続放棄をすることが多いケース
相続放棄相続放棄をするケースはさまざまです。 続する財産より借金の方が多そうで、相続したくない財産と借金の差がよく分からない親が亡くなったが、多額の借金がある亡くなった親の借金の督促が届いた親の住宅ローンをどうしたらいいか相談したい亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた このようなご相談が多いのですが、プラスの財産があっても相続放棄をされる方もいらっしゃいますし、借金があっても相続放棄を…
遺産分割
相続人全員によって相続財産を分ける手続きのことです。財産の分け方は遺言書に従ったり、相続人間による取り決めに従ったりする方法があります。遺言書に遺産の割合などが記されていても、相続人間で相談し全員一致で取り決めた場合には遺言内容と異なる分割をしても問題ありません。遺産分割はトラブルに発展するケースも少なくありません。
-
遺産分割とは
遺産分割遺産分割 民法第906条(遺産の分割の基準)「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」 遺産の分割とは、相続財産分割の客体となっている財産すべてを対象にして、総合的に行われます。共同相続人が、相続開始によって相続分にしたがって共有した財産です。他方で判例は、遺産分割前に共同相続人が合意の…
-
遺産分割協議
遺産分割遺産分割協議とは、相続人たちが被相続人の財産を誰がどのような割合で相続するかを協議するものです。まれに質問されることもありますが、遺産分割は5人なら5人でピッタリ5分の1ずつ分割しなければならないということではありません。遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、現物分割・換価分割など、どのような分割方法でも可能とされています。たとえば、共同相続人のうちの一部の者の取得分を0(ゼロ)にすることも可…
-
遺産分割協議書
遺産分割遺産分割協議書の効力 遺産分割協議をしたのちに遺産分割協議書を作成します。遺産分割の効力は、相続開始の時点にさかのぼります。遺産分割協議書は作成日から効力が発生するのではなく、被相続人がなくなった時までさかのぼり効力が発生するということです。相続開始後に遺産分割がされ遺産分割協議書が作成されたら、被相続人から相続した相続人個々人の財産になります。 遺産から生じた果実 被相続人か…
-
遺産分割をする相続人
遺産分割民法第906条(遺産の分割の基準)遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 遺産分割というのは、被相続人(亡くなった方)の財産すべてを各相続人で分割することです。この遺産分割についてを第906条が規定しています。 共同相続人はいつでも遺産分割をすることができます。被相続人が亡くなってすぐに…
遺言
死後に財産を誰にどう残したいかを記すことです。遺言書に記した内容は、法定相続分よりも優先して遺産分割を実現できます。さらに法定相続人ではない人にも財産を遺贈することが可能です。遺言を残さないと法定相続人ではない、たとえば友人などには相続する権利がありませんが、遺言書に意思を記すことで友人に遺贈することができるのです。
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。