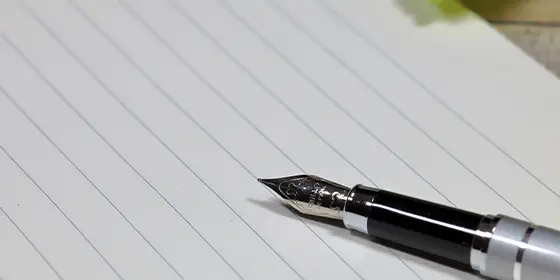相続の手続きをするには、どのような相続人がいるかを調査して相続人を確定しなければなりません。誰が相続人であるかは戸籍によって決まっていますので、戸籍を調べれば把握できます。しかし必ずしも明らかでない場合もあります。胎児の存在や、相続人の行方がわからない場合、婚姻外に子がいる場合などです。
胎児がいる場合
母体に胎児がいる場合、胎児は必ず出生するとは限りらなく、死産の場合もありえます。
胎児がいる場合も、胎児を除外して遺産分割をするのも有効という説もあります。胎児が出生したのちに民法第910条を類推適用するというものですが、この考え方は胎児の保護に薄いともいえます。
民法第910条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
特別代理人を選任して、胎児に代わり遺産分割協議ができるという説もあります。しかしこの場合は、もしも死産であった場合に困ります。また、胎児が双生児であると判明する前に遺産分割協議をし、双生児出生の場合も困ります。
胎児が現に出生するまで相続人の数が不明として、遺産分割協議を待つのがよさそうです。
相続人が相続承認後に行方不明の場合
相続人が相続を承認後に行方不明となった場合は、遺産分割協議ができないことになります。民法第907条第2項の適用となります。
第907条2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
つまり家庭裁判所で遺産分割の審判ができます。
相続人が相続開始当時から行方不明の場合
存在している相続人が、相続開始当時から行方不明の場合は、不在者財産管理人を選任し遺産分割協議ができます。
相続開始後で遺産分割協議前の死亡
行方不明の相続人が相続開始後で遺産分割協議前に死亡していたことが判明した場合は、相続人は存在した相続人の確定に重大な過誤はありません。行方不明で死亡した相続人の相続人となる者が、遺産分割協議に参加します。
同時死亡の推定がある場合
同時死亡の推定とは、たとえば父と子が同じ事故で死亡したような場合です。この場合、死亡者相互間には相続はおこりません。被相続人の先死が確認できる場合以外は、遺産分割協議を控えるべきです。
相続人身分の消滅が争われている場合
相続欠格・相続人の廃除・嫡出否認・親子関係不存在・婚姻または縁組の無効などが争われている場合がありますが、これらに該当する場合は、当該事件が解決し明確な判定が出るまで、遺産分割協議をすべきではありません。
被相続人の死後に認知の訴が提起された場合
被相続人が亡くなったあとに認知の訴がなされる場合があります。しかし戸籍上の相続人だけで、すでに遺産分割協議がされていた場合は有効です。民法第910条は有効を前提としています。
民法第910条
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
遺産分割協議を有効として、後に認知によって相続人に確定した者に、価額支払請求を許せばよいとしたのです。
非嫡出子の相続権
婚姻関係のある間に生まれた子を嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、法律上婚姻関係にない間で生まれた子どものことを非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。いわゆる婚外子や隠し子です。
婚姻外の子どもも父親が被相続人の場合、その父に認知されていれば相続人となります。相続分については、平成25年12月の民法改正により非嫡出子も嫡出子も同額となります。
(旧民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1という規定でした。)
たとえば、父親が被相続人で嫡出子Aと認知された子Bが相続人の場合、AとBは2分の1ずつを相続します。婚姻外の子も第一順位で相続人になります。正妻に子供がいなければ、正妻と2分の1ずつを相続します。
非嫡出子の認知について
認知とは、父親が婚姻外の子を自分の子であると認め、役所へ届出をすることです。父親本人が口頭で自分の子であると認めることは法律上の効力はありません。役所へ届け出る認知をすることで、婚外子は認知された非嫡出子の地位をえられ、父と子(母)の戸籍に記載されます。認知がされていない非嫡出子は、法的には父親がいないということになります。認知された非嫡出子となると相続人となれます。
ほかにも遺言によって認知する方法もあります。遺言書に記した内容は法的な効力が発生します。遺言書の内容として認められるものが法律で決められているためです。その遺言書の内容に子の認知が認められています。
父の死後3年以内に裁判所へ認知の請求をすることもできます。請求が認められた場合は、親子関係が認められ、相続権が得られることになります。3年を経過すると請求することはできません。
胎児の相続について
胎児は母胎内に存在していますが、出生していないません。民法は、胎児であっても、不法行為による損害賠償請求、相続(代襲相続を含む)、遺贈に限り、生まれたものとみなしています。
このように、胎児も相続人です。胎児の保護を考えて積極的に胎児の相続登記をおすすめします。
たとえば、妻が妊娠中に夫が死亡した場合、その相続財産は胎児にも相続されますので、相続財産の登記をすることができます。その後、もし胎児が死産したときは相続人に登記の抹消をされます。また、胎児を保護するために、胎児の出生前の遺産分割は無効とされています。
胎児の遺産分割についてはこちら
特別縁故者とは
特別縁故者とは、被相続人と特別親しい関係にあり、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる者のことをいいます。被相続人に法定相続人がいなければ、誰も財産を受け取ることはできません。相続人不存在の場合、最終的には国庫に納められることになります。
しかし法定相続人でなくても被相続人と特別に親しい者に財産分与を認めています。遺言がない限り財産を受け取ることができないのが原則ですが、「特別縁故者」として認められると財産の一部または全部を受け取れる可能性があるのです。特別縁故者は、あくまで相続人不存在の場合に限られます。たとえ相続人が行方不明でも音信不通でも相続人が一人でもいれば相続人がいるということです。被相続人が、不仲な相続人に相続財産を与えたくないという事情があっても相続人がいるということです。
第958条の2
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護につとめた者、そのほか被相続人と特別の縁故があった者が民法で定められています。
被相続人と生計を同じくしていた者は、文字通り被相続人と家計を同じくして生活していた者です。内縁関係、事実上の養親子・子の妻などが該当します。親族である必要はなく、長年生活をともにし、病気の際には看護につとめた者が特別縁故者として認められたケースもあります。
被相続人の療養看護につとめた者は、被相続人の生前に献身的に介護をした者です。同居していた者だけでなく、介護施設で看護した人が特別縁故者にあたることも考えられます。職場同僚であったり、従業員が該当するということもあります。対価を得て仕事として看護をした者は当てはまりませんが、対価以上に看護に尽力した者が該当した判例もあります。
そのほか被相続人と特別の縁故があった者は、上記以外の者で上記に相当するほど密接な関係があった者です。被相続人の生前に生活上の支援をしていた者が認められています。特に親しくしていた友人知人、金銭的な援助を受けた人などです。
特別縁故者と認められる法人・団体
被相続人が密接に関わった法人が認められることもあります。学校法人や宗教法人、法人格のない団体など、法人・団体が特別縁故者として認められることもあります。
相続人不存在の場合はどうなる?
被相続人に子がなく、法定相続人も特別縁故者もいないという場合、財産は最終的に国庫に納められます。土地や建物などを他の人と共通している共有財産は除きますが、被相続人の固有の財産であれば国に帰属します。
特別縁故者の財産分与手続き
特別縁故者の財産分与手続きは、特別縁故であるという関係を主張する者自身が申し立てます。たとえば内縁関係の妻が特別縁故だとして自動的に財産分与されるわけではありません。特別縁故者への財産分与の申立ては、相続人不存在の確定後3ヶ月以内に家庭裁判所に自身で申立てをして、認められなければなりません。期限を過ぎると財産を受け取れなくなってしまいます。
特別縁故者が財産分与の申立てをせずに死亡した場合は、その者の相続人は特別縁故者の地位を引き継ぐことはできません。申立てをしたのちに死亡した場合は、一種の期待権として相続されます。
普通養子縁組と特別養子縁組
普通養子縁組は、養子と実親との親子関係は継続したまま、養親と親子関係となります。特別養子縁組は、実親との親子関係を断ち、養親が養子を実子と同じ身分という扱いにすることです。
普通養子の相続
養子縁組によって養子となった者が、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。養子は、養親の嫡出子の身分を取得するので、養親の相続は実子と同じ順位で相続人となります。養子縁組によって兄弟姉妹となった者の相続も相続人となります。また、実子と養子で法定相続分に違いはありません。
普通養子縁組による養子は、養子縁組をしても実親との親子関係が継続しますので、普通養子は実親の相続において第一順位の相続人です。実親の子の相続の場合、兄弟姉妹として第三順位である相続人という立場も変わりません。さらに、普通養子が死亡した場合、実親のと同様に養親も直系尊属として、養子の相続の第二順位の相続人になります。実親と養親の相続分は均等で、たとえば養父母、実父母の4人が相続人なら、各四分の一となります。
もし離縁によって養親子の間の法的な親子関係が解消され、他人となります。つまり、養親と養子の相続関係は生じません。ただし、離縁する前に開始した相続は、相続人という立場を有します。たとえば、養父が亡くなったあとに離縁の手続きをして親子関係を解消した場合、養子(離縁後の他人)は元養父の相続人として相続することができます。
特別養子の相続
特別養子縁組によって養子となった者は、養親にとって実子と同等となるので相続における扱いも同様です。特別養子は養親の相続人となります。養親の子(養子の兄弟姉妹)の相続でも相続人となります。また、実子と養子で法定相続分に違いはありません。
普通養子と異なるのは、実親との親子関係は終了している点です。そのため特別養子は、実親または実親の子(養子にとって兄弟姉妹)の相続人となりません。特別養子が死亡した場合、養父母は特別養子を相続しますが、実父母は相続することはありません。
養子の代襲相続
子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であることと、非相続人の直系卑属でなければなりません。養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続しません。養子縁組前に生まれた養子の子は、養親との間に血縁関係がないためです。反対に、養子縁組後に生まれた養子の子は、養子縁組で養親と法的に親子となります。そのため代襲相続人となります。
代襲相続はこちらでも解説しています。
相続人の資格の重複
相続人としての資格が重複する場合があります。つまり、一人に2つの相続人としての身分が重なる場合があるということです。民法上、法定相続人になりえるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。一人の相続人が、重複してこれらの身分を持ち合わせるケースが存在します。
相続人としての資格が重複した場合、相続分の決定は民法に明確に定められているわけではありません。遺産の割合は相続人がどれだけの法定相続分を有するかが重要です。
第887条
1. 被相続人の子は、相続人となる。
2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第889条
1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹
重複した資格の例
ケース1
祖父母が孫を養子としたケースでは、子と孫としての身分の重複から相続資格が重複します。
ケース2
父母が子の配偶者を養子としたケースでは、配偶者と兄弟姉妹としての身分の重複から相続資格が重複します。
ケース3
被相続人の実子長男・次男・長女といた場合に、長男が長女を養子とし、のちに長男が死亡、その後被相続人が死亡した場合、被相続人の長女は被相続人の子としての相続資格と、長男(兄)の子(養子)としての代襲相続人となる相続資格が重複します。
登記実務
養母の養子となっている夫婦(夫A・妻B)において、妻Bは夫の妹でもあります。戸籍・除籍謄本および相続放棄申述受理証明書のほか、妻Bの配偶者として相続放棄をしたことを確認できる相続放棄申述書の謄本、さらに夫(兄)の妹としては相続放棄をしていない、とした相続登記の申請について、これを受理して問題ないとしています。
ほかの例では、被相続人の養子が相続放棄をして、のちに死後認知の裁判が確定しても、その養子は非嫡出子としての相続権を持っていないとしたものがあります。認知には遡及効(さかのぼって効力が生じる)があるため、相続開始のときには非嫡出子であったことになります。しかし養子と非嫡出子という資格は、相続関係では両立しないとしたものです。
相続欠格
民法第891条に定めるとおり、相続人が相続する権利を失ったり、剥奪されたりする制度です。本来であれば相続できる権利をもつが、特定の事由によって相続人になることができなくなります。
ただし、相続欠格は別の相続に影響しません。たとえば、父親の相続で欠格事由に該当して相続権を失っても、母親の相続では関係ないので母親からの相続権は有効です。
また、相続欠格は代襲相続(被相続人の死亡以前に相続人が相続権を失ったとき、他の者が相続人となる制度)にも影響しません。たとえば、祖父の相続に対して父親が相続欠格であったとしても、孫は父親の相続欠格とは関係なく、祖父と孫の間に相続欠格の事由がないなら、孫は代襲相続人として有効です。
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格の事由
民法第891条の欠格事由を下記に解説します。
その1
故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺したり、殺そうとしたりしようとして、刑罰を受けた者です。執行猶予となった者は、執行猶予期間を満了ののちに、相続欠格事由がなかったことになるのが一般的です。
その2
被相続人が殺害されたことを知ったが告発せず、または告発しなかった者です。ただし、善し悪しの区別が判断できない者(幼い子ども、精神を患い判断能力がない者など)、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族(子や親)である者は相続欠格となりません。
その3・その4
自分に都合のよい遺言を書いてもらうために、詐欺や強迫をした者です。遺言者の意思のとおりに遺言をのこすことを妨げる行為、自分に財産が渡るような内容にさせたり、自分に不都合な内容を撤回させたり、取り消しさせたり、変更させたりする行為は相続欠格の事由になります。
その5
遺言内容が、自分にとって都合がよくないために遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした者です。自筆証書遺言の場合、遺言をのこした事実は遺言者本人しか知りません。遺言者本人がどなたかに知らせていたり、誰もがわかる場所に置いていたり、法務局に保管(自筆証書遺言保管制度)をしていたりしない限り、遺言書があることが知られない可能性もあります。
たとえば、第一に発見した者が内容を見て、自分には都合がよくないと知り、偽物を作成したり、遺言内容を書き換えたり、捨てて無かったことにしたり、隠したりする行為は相続欠格の事由になります。
遺産分割協議後に相続欠格が判明した場合
遺産分割協議によってそれぞれの分け方が決定したあとというのは、遺産分割協議をやり直すことができません。しかし、例外として、遺産分割協議後に特定の相続人に相続欠格の事由がみつかったとき、遺産分割協議をやり直すことが認められます。
すでに終えた遺産分割協議は、相続人ではない人が参加した協議になるためやり直しが必要になるのです。
相続人廃除
民法第892条に定めるとおり、推定相続人(相続が開始した場合に相続人になることが推定される人)に著しい非行がある場合、相続権を剥奪する制度です。
相続欠格と異なる点は、法律にもとづいて相続権を失うというのではなく、被相続人の意思にもとづいて相続権を失うということです。
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
相続人廃除の事由
被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱
虐待とは、被相続人へ暴力や精神的な苦痛を与えることです。重大な侮辱とは、被相続人の名誉や感情を著しく害することです。
そのほか著しい非行
被相続人との信頼関係を損なう非行、重大な精神的負担を与える非行です。
これら虐待や侮辱、非行は判別が難しい行為でもあります。被相続人と相続人がケンカをした、というものでは認められません。このようなすべての行為が廃除理由となるわけではありません。よっぽどの行為でないと該当しないといわれています。
以下のような判例があります。
- 推定相続人である子が、被相続人の所有している土地にビルを建てたいと言い出した。被相続人が反対すると、推定相続人が被相続人にビンを投げつけたり、玄関のガラスを割ったり、さらに放火すると脅しました。被相続人ら家族は、やむなく他所へ避難。被相続人への虐待とされ、廃除が肯定。(昭和63年 東京家庭裁判所八王子支部審判)
- 被相続人が再婚したころから長男は被相続人に敵対的な態度だった。被相続人の再婚相手が亡くなったあとも、長男は被相続人の近所に暮らしていたにもかかわらず被相続人の面倒をみることもなかった。さらに被相続人の再婚相手の遺産をめぐって対立し、「早く死ね」など罵倒した。被相続人への重大な侮辱とされ、廃除が肯定。(平成4年 東京高等裁判所)
- 被相続人夫婦と縁組し、夫婦の二女と婚姻した相続人は、被相続人から居宅・賃貸用家屋の贈与など援助を受けた。しかし被相続人が重病になっても看病や見舞いもなく、それどころか妻子を捨て別の女性と逃げ、姿をくらました。被相続人への重大な精神的苦痛を与える著しい非行であるとされ、廃除が肯定。(昭和55年 横浜家庭裁判所審判)
- 大学進学後に生活が荒み、学業は放棄、家族に当たり散らし、暴れ回って金を要求、仕事に就かず浪費を重ねた相続人は、被相続人への著しい非行とされ、廃除が肯定。(昭和42年 東京家庭裁判所審判)
- ギャンブルを繰り返して作った多額の借金を被相続人に支払わせ、妻子をかえりみず愛人と同棲していた相続人は、著しい非行であるとされ、廃除が肯定。(昭和63年 青森家庭裁判所八戸支部審)
相続人廃除の手続き
相続人廃除の手続きは、被相続人が生前に自己の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。家庭裁判所が審判し、認められることで廃除となります。
大まかな流れは、被相続人が必要書類を用意し、家庭裁判所に申立書とともに提出します。申立人と廃除の対象者(相続人)で廃除事由の主張や立証を経て、家庭裁判所が判断をします。廃除が認められたら、ただちに各書類を持って市区町村へ届け出ます。
のちに被相続人が廃除者への考えを改め、廃除を取り消したいと思えば、取り消し請求をしたり、遺言によって取り消したりすることができます。
相続ガイド相続・遺言・相続放棄を分かりやすく解説
相続・遺言・相続放棄について、分かりやすく解説した「相続ガイド」です。
民法における相続のルールを、条文をもとに解説しています。
気になるキーワードで検索をして、お求めの解説を探せます。
当サイトの相続ガイドは、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。