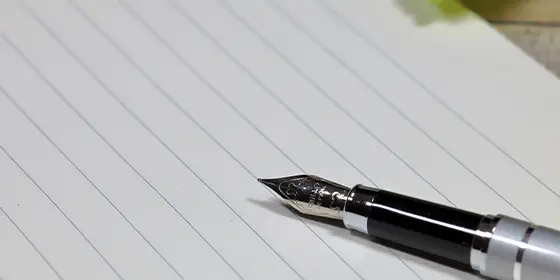遺産分割
民法第906条(遺産の分割の基準)
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
遺産の分割とは、相続財産分割の客体となっている財産すべてを対象にして、総合的に行われます。共同相続人が、相続開始によって相続分にしたがって共有した財産です。他方で判例は、遺産分割前に共同相続人が合意のうえ相続財産の中の不動産を売却した場合、その代金(代償財産)は、もはや遺産分割の対象ではなく一般財産法上の財産として扱われるとしています。
また、相続財産に属する財産から賃料など(法定果実)が生じた場合です。
判例では、各共同相続人が相続分に応じた大きさではあるものの遺産ではない分割単独債権として確定的に取得するとしています。しかも、遺産分割によって果実を生んだ元物が誰に割り付けられても、そのことは果実の取得に何ら影響を及ぼさないとしています。
さらに、過分の権利であるため相続開始時に各共同相続人に、相続分に応じて分割される権利(預貯金債券以外の過分債権など)も、実務では共同相続人の合意がない限り、総合的分割の対象ではないとされています。相続における財産分けが実態上、相続開始後比較的短期間のうちに一挙に行われるとは限らず、五月雨式にされると考えれば、これらの処理は仕方がないと思えます。
しかし、総合的分割としての遺産分割の中で一括処理を指向しないことは、法定相続における共同相続人間の平等を害することを許容することになりかねません。
遺産分割の方針は、あらゆる事情を考慮してされるべきです。相続財産を誰にどのような割合で分割するか、につきます。つまり民法第906条の規定にあるように、遺産分割は、遺産に属するものまたは権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他のすべての事情を考慮されなければなりません。
もっとも、遺産分割協議で共同相続人全員の合意があれば、法の規定によって算出される割合(つまり法定相続分)とは異なる分割にもなります。実質的には、共同相続人間での贈与があった、と考えることができるためです。
遺産分割の前に財産が処分された場合
遺産分割を協議する前に、遺産に属する財産が処分された場合についての遺産の範囲は、民法第906条の2に新規に規定されました。
第906条の2の1は、遺産分割前に遺産分割の対象である財産が処分された場合に、共同相続人の合意によって、その処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するものをみなし、遺産分割の対象とすることができる旨を定めています。
第906条の2の2は、1項の処理をするにつき、処分をした当該共同相続人の同意を不要としています。
第906条の2
1.遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2.前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
ここでいう処分は、典型的には、各共同相続人による分割前の遺産の持分の処分です。この処分があった場合、残った遺産を具体的相続分によって分割することになりますが、率分としての法定相続分と具体的相続分の間の差や処分の価額によって、処分がなかったときに生じたはずの結果と違いが生ずることがあります。
このようなケースを踏まえて、典型的には遺産分割に際して、分割に先立って処分された財産を処分した共同相続人に、その同意を必要とせずに仮想的に割り付けることを可能にしたものです。
第三者による遺産の処分
本条にいう財産の処分は、共同相続人に限らず第三者による処分も含まれます。第三者による処分の場合には、各共同相続人は第三者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求や不当利得返還請求をすることになります。遺産分割においては、当該遺産が現存するものとみなして、協議することも可能にななります。