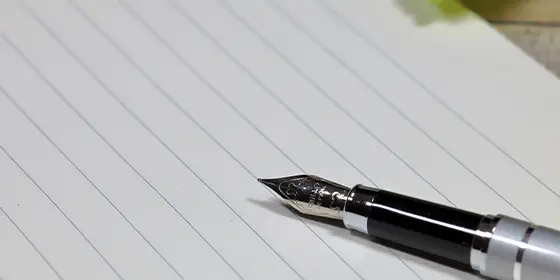配偶者の相続権の規定
配偶者が死亡した場合の相続について、民法第890条が定められています。
婚姻の死亡解消に際して相続という方法で、財産関係の清算をするというものです。
民法第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
死亡した配偶者の他方配偶者が相続人となるためには、婚姻届を出していなければなりません。つまり法律上の配偶者であることが必要です。これは戸籍上から配偶者として相続人であると推定されないと、取引の安全を害するからです。
重婚の一方の取消判決の確定に先立って、それぞれの重婚者につき相続が開始している場合が問題です。 この場合、いずれの配偶者にも相続権が認められます。
同時存在の原則との関係
同時存在の原則とは、相続開始時に相続人が生存していなければならないことをいいます。
たとえば、夫婦が同時に交通事故で死亡した場合、夫婦には子どもがなく、ともに両親も死亡していたとします。同時存在の原則で、夫婦は相互に配偶者としての相続権はありません。両親も死亡しているため、夫については夫の兄弟姉妹が相続します。妻については妻の兄弟姉妹が相続します。
内縁配偶者
法律上の配偶者でない内縁配偶者に相続権はありません。長年連れ添った事実上の夫婦であっても、内縁が破たんして解消した場合は、財産分与請求権が認められています。
これを類推適用して、死亡解消の場合に生存配偶者を保護できるかという疑問もあるかもしれません。平成12年3月10日の最高裁判所の判決では、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与請求ができないとしています。婚姻という籍を入れることの重大さを判決で認めたかたちです。
なお、内縁関係の間の子は、婚姻関係のない間に生まれた子として非嫡出子といいますが、原則、相続権がありません。非嫡出子は、認知されることで相続人となります。被相続人と血のつながりがない場合(たとえば、内縁の妻の連れ子)の場合は、養子縁組をしていれば相続人として認められます。非嫡出子であっても嫡出子であっても相続分は同等です。